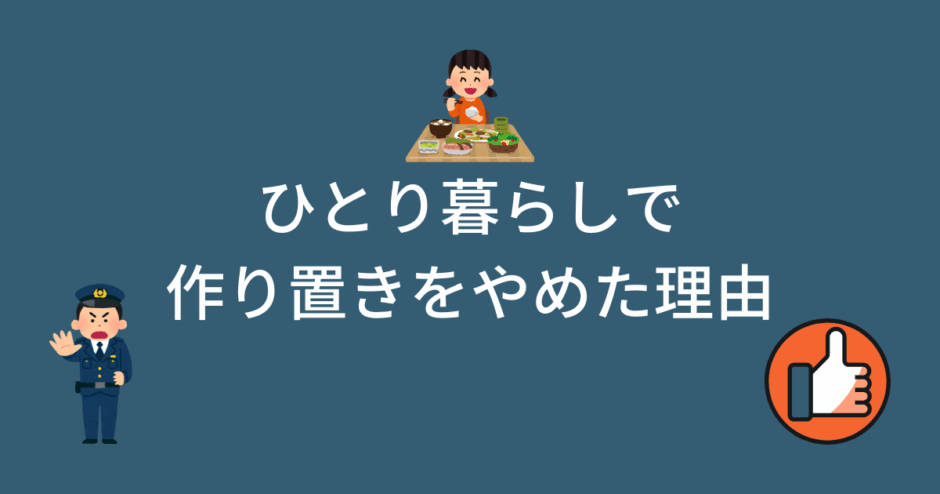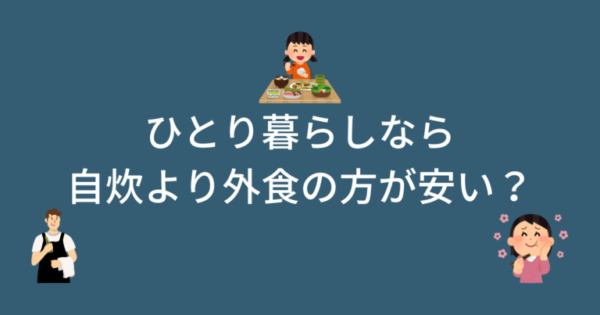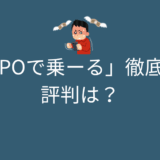【PR】本ページはプロモーションが含まれています
- 作り置きをやめた理由
- 作り置きをやめても、外食に頼りすぎたくない
一人暮らしで自炊を続けていくためには、作り置きをは強い味方です。作り置きをしていれば、平日の忙しい夜でもサッと夕飯が食べられるので、頑張っていてよかったと感じることでしょう。
でも作り置きは結構な負担となるので、長くは続けられず、作り置きをやめた!という方もいます。
この記事では、メリットがあることはわかっていても続けられない作り置きについて、「作り置きをやめた理由」や「作り置きをやめた後でも外食に頼らない方法」を紹介します。
-- この記事のもくじ --
一人暮らしの人が作り置きをやめた5つの理由
ひとり暮らしをはじめるとき、自炊を頑張ろうとしてキッチン道具や家電をそろえる方もおおいのではないでしょうか。
でも仕事から帰ってから夕食を作ろうとしても「家に着くのは7時過ぎてる」「仕事で疲れてご飯を作るのはしんどい」なんてことになることもよくある光景です。
そんな忙しい平日対策に有効なのが「作り置き」ですよね?
ただ「作り置き」は便利な反面、やめてしまう人もおおく続けることが難しいという一面もあります。ではどんな理由でやめてしまうのかを解説していきます。
1. 1週間分の作り置きは疲れる(週末がつぶれる)
ひとり暮らしで作り置きを頑張ろうとすると週末の休日などを使うことがほとんどです。
料理が得意か不得意かにもよりますが、1週間分の作り置きをしようとすると、料理をつくるだけでなく、食材の買い物にも行かないといけないので、1日がかりの大仕事で、せっかくの貴重な休みが料理で1日つぶれてしまいます
そのため「料理が苦手な人」や「好きでもない人」からすると苦痛以外のなにものでもありません。
最初はやる気でカバーできますが、長く続けようとすると「料理が楽しい」「料理が好き」でないと続けることは難しいと言えるでしょう!
2. 1週間分の作り置きをするには冷凍庫が小さい
ひとり暮らしで作り置きをするときに問題となるのが「冷凍庫が小さい」という現実です。
ひとり暮らし用の冷蔵庫は大きくても150Lぐらいです。また1Rや1Kの家に住んでいる方がおおいので、そもそも冷蔵庫が大きいものが置けないという制約もでてきます。
そのため、1週間分の作り置きをするにも冷凍庫に入りきれません。また最近は、ふるさと納税の返礼品で冷凍庫をつかうことも増えているので、作り置きで冷凍庫を使えないということもあります。
物理的な制約で作り置きができないということで、やめる人もおおくいます。
冷蔵庫の日持ちの目安は3日
冷凍庫の保管に限界があるから冷凍庫に保管しようとしても、日持ちの目安は3日です。それ以上、冷蔵庫に入れておくと雑菌が繁殖したりして食中毒などの危険性がたかまります。
そのため、1週間分の作り置きをしようとすると冷凍保存は避けては通れません。
3. 食材を使いきれない(毎日同じメニュー)
お肉、野菜、魚などをスーパーで買うと、ひとり暮らしには少し大きいと感じることがありませんか?
また、まとめて買ったほうが安かったりするので、少しおおめに買うこともあるでしょう。
でも、同じ食材を使って豊富なメニューをつくるのには料理のレパートリーがないとできませんし、余計に手間もかかります。そのため、一品を大量に作るということになります。
こうなってしまうと、毎日同じメニューを覚悟しないといけません。今日の食べたいものがなんであれ、家に帰ればメニューは昨日も食べたものになることは当たり前になるので、続けていけなくなる人がいるようです。
4. 味が落ちる
作り置きは、出来立てに比べて味が落ちます。料理によっては、1日置いた方が味が染みておいしくなったりするものもありますが、やはり出来立てが一番おいしいく感じますよね。
最近の冷蔵・冷凍庫は昔に比べると味が落ちずに保管できるようになっていますが、やはり出来立てには勝てません!
毎日おいしいものを食べたいという人には、手間をかけて作った作り置きがおいしく感じないと続ける意欲もわかなくなるのは当然かもしれませんね。
5. 急な予定に対応できない
平日の調理は一切なく全て冷凍の作り置きであればいいですか、平日にメインや副菜だけを自炊するという人であれば、冷蔵庫に野菜やお肉などがあるはずです。
そんなとき、上司や先輩から晩ご飯や飲みに誘われることもあります。
計画していた予定が狂ってしまって、食材を腐らせてしまうと「もったいないな」と思うことになるでしょう。このようなことが重なると自炊をすることが難しくなるので、自炊と一緒に作り置きもやめてしまうという人がでてきます。
作り置きをしてまで自炊を続ける理由は?
2024年4月に「簡単宅食ガイド 宅食グルメ」が、ひとり暮らしの18~29歳の男女469人を対象に、自炊についてアンケート調査しています。
- 「ほぼ毎日自炊している」割合は、29.0%という結果でした。
- これに「週4~5回」「週2~3回」も含めると、76.4%もの人が日常的に自炊をしていることが分かりました。
ひとり暮らしの4人に3人が自炊をしているという意外な結果ですね。では、これだけの人が、なぜ「作り置き」という手間をかけてまで自炊を続けようとするのでしょうか?
「自炊をする理由」についてみてみましょう!
- お金を節約したい(50.4%)
- 健康的な食生活を送りたい(15.8%)
- 手作りのものを食べたい(10.8%)
- 料理が趣味だから(10.1%)
- 食の安全性が気になる(8.9%)
想像の通りですが、自炊は節約のためのようですね。節約のために、一生懸命作り置きを頑張っていることが分かりました。
でもたまには自炊できない日もありますよね?「自炊できない日の理由」をチェックしましょう!
- 時間がない(168人)
- 疲労や体調不良(147人)
- 料理する気分ではない(138人)
時間の問題や体調・気分などがあるようです。逆に言えば、このような日のために多くの人が「作り置き」をしていることが想像できますね。
自炊を続けるための「作り置き」以外の方法
ここまで見てきたように、節約のために自炊を頑張る人はたくさんいます。ただ、そんな人たちでも平日は忙しくて自炊ができないこともあるようです。
そのため、休日に「まとめて作り置き」をすることで忙しくても外食に頼らない生活を送っています。
ただそんな頑張りはずっと続けていくことは至難の業です。どこかで限界がきます。
自炊を続けていくためにも、作り置きだけではない「作り置き」に代わる方法を覚えておきましょう!
1. 肉や魚などの缶詰を常備しておく
スーパーにいけば、焼き鳥やさばなど豊富な種類の缶詰が売っています。
缶詰は調理済みのものばかりなので、ふたを開ければすぐに食べることができます。ごはんを食べる方は、炊いたご飯を冷凍しておくか、パックご飯のどちらかがあればすぐに食べられますよ。
2. 冷凍食品をフル活用する
冷凍食品は、おかずから野菜まで種類は豊富にあります。
スーパーの冷凍食品コーナーにいけば、ハンバーグ・揚げ物・スパゲティ・餃子などのメイン料理から、ホウレン草やブロッコリーなどのカット野菜など外食のメニューと同じようなものが見つけられるはずです。
お手頃の値段で買えるものもおおいので、好きな冷凍食品を買って冷凍庫に保管しておけば、仕事から帰ってすぐレンジでチンするだけで食べれますよ。
3. 時短レシピを覚える
共働き家庭も増えてきているため、時短レシピやレンジだけで調理できる手間いらずな料理などのレシピ本がたくさん売っています。
また、Youtubeなどでは時短料理などがたくさん投稿されています。
時短レシピを覚えることで、仕事から帰った後でも、なんとか時間を確保して自炊を続けることができるかもしれませんね。
4. 宅食を活用する
共働き世帯などでの活用することが多いのですが、ひとり暮らしでも宅食はとても便利です。
とくに冷凍で届く宅食であれば、賞味期限も気にせず、好きな時にレンジで温めるだけで、外食と同じようなクオリティの料理を自宅で食べることができます。
また、宅食によっては「FIT FOOD HOME」のように、無添加にこだわって安心安全に食べれるものがあります。
「健康的な食生活を送りたい」「食の安全性が気になる」というような人でも取り入れやすい方法です。
5. 家事代行で作り置き
少し贅沢ですが、家事代行で作り置きをしてもらうという手段もあります。
- 忙しくても手料理が食べられる
- 栄養バランスに配慮した食事になる
- 食べたいメニューをリクエストできる
- 自分の時間ができる
メリットはたくさんあり、とても魅力的です。
ただ、最大のデメリットは食材費は別で、依頼料が1時間あたり3,000~4,000円かかるということです。月50,000円程度の予算は考えておかなければなりません。
主な対象は共働き世帯向けのサービスですが、ひとり暮らしでも使っている人はいますので、検討してみてはいかがでしょうか?
End.